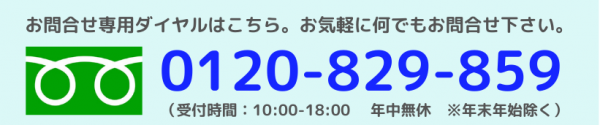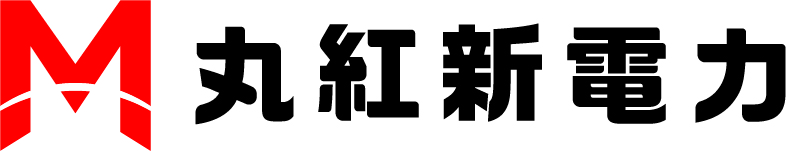蓄電池は寿命が来ても使えるの?-丸紅エネブル蓄電池
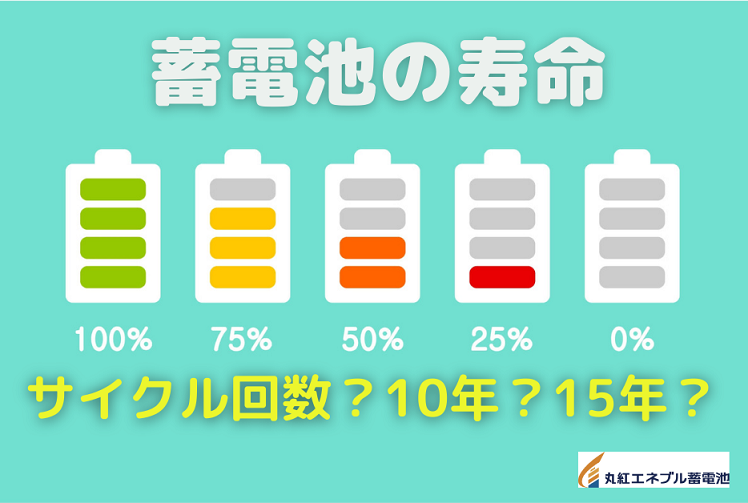
蓄電池は、光熱費の削減や非常時の備えと便利に感じますが、肝心なのはいつまで使えるのかですよね。
導入するとなるとそれなりの費用が必要なので、「蓄電池の寿命って?」「寿命が来た後も使えるの?」といった疑問は自然に浮かんでくるでしょう。
そんなあなたのために、ここでは蓄電池の寿命の基本はもちろん、目安の年数まで詳しく解説していきます。
最後に、蓄電池を長持ちさせるための秘訣も併せて紹介するので、ぜひ一度目を通していってください!

史上最高のポータブル電源 ECOFLOW「DELTA PRO」特設ECサイトにて絶賛発売中(←click here)
蓄電池の寿命はどのくらい?
そもそも蓄電池は、どのくらいの期間持つものなのでしょうか。
実は、蓄電池の寿命の考え方は、一般的なものの寿命とは少し考え方が違います。
まずは、蓄電池の寿命の基本から確認していきましょう。
蓄電池の法定耐用年数6年は寿命と無関係
蓄電池の寿命の話題になると、法定耐用年数の6年という数字を見かけることがありますが、製品としての寿命とは全く関係ありません。
法定耐用年数とは、国税庁が固定資産税を計算するために便宜的に定めた年数です。
法定耐用年数6年の蓄電池であれば、6年で減価償却を迎えるため、税法上は6年以降の資産価値がゼロになります。
つまり、蓄電池の寿命と法定耐用年数の6年という年数は、直接的には関係がないというわけです。
蓄電池の使用年数が法定耐用年数の6年を超えたとしても、蓄電池が寿命を迎えて使えなくなるわけではありませんので安心してください。
蓄電池の寿命はサイクル回数で決まる
そこで蓄電池の寿命を表す指標として用いられている概念が、サイクル回数です。
サイクル回数とは、蓄電池の充電と放電の1セットを1サイクルとして、充放電を何回まで繰り返せるかを示した単位を指します。1サイクルのカウント方法は、蓄電池の完全放電→満充電→完全放電の1周分で1サイクルです。
つまり、蓄電池の残量が0%の状態から100%まで充電し、そこからまた0%になるまで放電するという1往復が1サイクルとなります。
蓄電池は充電と放電を繰り返し行いますが、普通に使っている分には残量0%の完全放電を行うことはありません。完全放電すると、そのバッテリーは使えなくなってしまうためです。
通常は30%や50%など、あらかじめ蓄電池に設定した放電深度に応じた残量までしか放電されませんので、単純な充放電1回だけでは1サイクルに達しません。あくまで、サイクル回数は充放電の往復した幅の積み上げでカウントするのです。
そのためサイクル回数は、設定した放電深度はもちろん、メーカー特性から蓄電池の使い方、周辺環境などの使用条件によって大きく変わります。
このように蓄電池の寿命は、サイクル回数が変動するために単純な年数では表現されません。
ただ、おおよその蓄電池の寿命を知りたいのであれば、1日あたりのサイクル回数を1回として計算すれば、安全を見たおおよその年数でわかります。たとえば、寿命が8,000サイクルの蓄電池であれば、8,000サイクル÷365日=約22年は最低限使えそうだ、と想定できるわけです。
最近では、12,000サイクルを謳う製品も出てきています。
寿命の目安は蓄電池のメーカー保証年数
蓄電池の寿命はサイクル回数で決まるとはいえ、メーカーによってはサイクル回数自体を公表していないところもあります。また、蓄電池が具体的にどのくらいの年数だけ使えるのか、サイクル回数では実際の寿命をイメージしにくいですよね。
そこで、蓄電池の寿命の目安となっているものが、メーカー保証年数です。
一般的に蓄電池の寿命というと、このメーカー保証年数を指します。
蓄電池のメーカー保証には、機器の瑕疵保証に加えて、蓄電池の容量保証が備わっています。
機器の瑕疵保証は、メーカーの基準通りに使用していたにもかかわらず、故障や不具合が発生した場合にメーカーが無償で交換・修理対応する保証です。
こちらは、エアコンや洗濯機などの一般的な電化製品でもありますね。
瑕疵保証は、蓄電池本体はもちろん、蓄電池用パワーコンディショナーなどの周辺機器にも適用されます。
一方で蓄電池の容量保証は、メーカー保証期間内に蓄電池容量が一定値以下にならないことを保証するものです。つまり、メーカー保証年数以内であるにも関わらず、蓄電池の容量が保証容量以下になったとき、メーカーが無償で保証してくれます。
この容量保証が、蓄電池の寿命と言われるものです。
実際に容量保証の年数や容量がどのようになっているのか、いくつか蓄電池メーカーの設定値を見てみましょう。
|
メーカー |
パナソニック |
シャープ |
オムロン |
ニチコン |
|---|---|---|---|---|
|
型番 |
LJB1156 |
JH-WB1621 |
KPAC-B |
ESS-H1L1 |
|
保証年数 |
無償10年、 |
無償10年、 |
無償15年 |
無償15年 |
|
容量保証 |
定格容量の60%以上 |
定格容量の60%以上 |
定格容量の70%以上 |
定格容量の50%以上 |
表からわかるように、無償・有償の違いはあれど、どの蓄電池メーカーも10年もしくは15年を保証年数として設定しています。
つまり、蓄電池の寿命は、10年・15年が1つの目安といえるでしょう。
蓄電池は寿命を迎えると使えなくなる?
では、蓄電池はメーカー保証年数を迎えると、寿命が来て全く使えなくなってしまうのでしょうか。
結論から言えば、そんなことはありません。
ここでは、蓄電池が寿命を迎えるとどうなるのかを解説していきます。
寿命を迎えた蓄電池は最大容量が減る
蓄電池は、メーカー保証年数を迎えると充電可能な最大容量が減ります。
ただ、メーカー保証年数を迎えたときに突然、最大容量が減るわけではありません。
蓄電池は、使用していくにつれ徐々にバッテリーが劣化していき、最大容量が少しずつ減少していくのです。
最大容量の減少具合は、前章の表から見るに、10年〜15年で約50%〜70%程度まで減少するとわかります。たとえば、容量7.0kWhの蓄電池であれば、およそ3.5kWh〜4.9kWhまで充電できる容量が減るわけです。
もちろん、蓄電池の使い方や周辺環境によって増減しますが、最低限50%は残るといえるでしょう。
蓄電池は寿命が来てもまだ使える
蓄電池は、メーカー保証年数を迎えると充電可能な最大容量が減るものの、蓄電池として機能するまではまだまだ使えます。そのため、メーカー保証年数を迎えたからと言って、寿命で蓄電池をすぐに交換しなければならないわけではありません。
ただ、最大容量が減るということは、蓄電池の利用効率が悪くなることを意味します。
最大容量が50%減少すれば、単純計算でその効率は半減です。
そのため、寿命を迎えた蓄電池は、導入した当初のような効果は期待できません。
とはいえ、最大容量の50%〜70%もあれば、十分に蓄電池としての機能を果たしてくれます。
そのまま使い続けて問題はないでしょう。
ただし、蓄電池のバッテリーが寿命を迎えていなかったとしても、油断はできません。電子部品の多い蓄電池は、他の部分が先に寿命を迎える可能性は十分にあります。
たとえば、蓄電池内部の基盤やパワーコンディショナーなどの周辺機器が挙げられるでしょう。
そのため、蓄電池を長く利用するためには、定期点検やメンテナンスで蓄電池の状態をよく把握しておく必要があります。
蓄電池メーカーの容量保証を上手に活用しよう
使用年数とともに最大容量が減った蓄電池は、容量保証を上手に活用することで交換費用なしで蓄電池を蘇らせることが可能です。
容量保証は、条件を満たしていれば蓄電池メーカーが無償で対応してくれるので、利用しない手はありません。ただし、容量確認の作業費や出張費などは、メーカーによって実費がかかることもあるため事前によく確認しておきましょう。
また、容量保証を適用させるためには、購入時にメーカーへ申し込みが必要な場合が多いため、申請漏れのないように注意したいです。
蓄電池の寿命を延ばす3つのポイント
長く蓄電池を使えれば、それだけ投資対効果が高まるので、できる限り劣化しないように気をつけたいですよね。蓄電池は、サイクル回数を重ねるごとに劣化するため、蓄電池の使い方や周辺環境が寿命に大きく影響するのでした。
ここで紹介する3つのポイントに注意して、蓄電池の寿命を延ばしていきましょう。
- 適した動作環境で蓄電池を使う
- 過充電や過放電をしない
- 蓄電池対応の太陽光発電と接続する
適した動作環境で蓄電池を使う
蓄電池の寿命を延ばすポイントの1つが、動作に適した環境で蓄電池を使用することです。
蓄電池は、充放電するときにバッテリー内の電解液の化学反応を利用しているため、高温・低温を苦手とします。スマートフォンのバッテリーをイメージすると、わかりやすいでしょう。
高温は自己放電によるダメージを与え、最悪の場合は発火や破裂の危険性があります。一方で、低温下であれば内部抵抗が大きくなり、蓄電池として機能しなくなります。特に、直射日光の当たる場所や熱のこもりやすい通気性の悪い場所、寒冷地へは蓄電池の設置を避けましょう。
また、湿度が高いと内部結露によって蓄電池の故障や不具合に繋がるため、湿気のこもりやすい場所も避けるべきです。蓄電池メーカーは、機種ごとに正常動作ができる温度や湿度範囲を設定しているので、そちらを遵守するようにしましょう。
過充電や過放電をしない
過充電や充放電をしないことも、蓄電池の寿命を延ばすポイントの1つです。
過充電・過放電とは、充電もしくは放電しすぎることをいいます。具体的には、満充電状態でさらに充電することが過充電、完全放電状態で長時間放置することが過放電です。
過充電・過放電のいずれも、蓄電池に対して深刻なダメージを与えてしまいます。
程度によっては修理で対応できずに、バッテリー自体を交換しなければならなくなってしまうでしょう。
もちろんメーカー保証の適用外になりますので、有償対応となります。
ただ、現在販売されているほとんどの蓄電池は、制御を最適化するバッテリーマネジメントシステムというプログラムが働いています。バッテリーマネジメントが、過充電や過放電にならないように制御を行ってくれるのでそこまで心配する必要はありません。
蓄電池を導入するタイミングで、利用を始めるまでの時間が空く場合には注意したほうが良いでしょう。
蓄電池対応の太陽光発電と接続する
太陽光発電と蓄電池を併設する場合、必ず蓄電池対応の太陽光発電と接続しましょう。
蓄電池は、太陽光発電と連携してさらに効果的な利用が可能になる一方、相性の問題もあります。
相性の悪い太陽光発電と接続してしまうと、蓄電池の劣化を招く可能性を否定できません。
最悪の場合は、蓄電池の不具合や故障に繋がります。蓄電池だけでなく太陽光発電も同様に、悪影響を受けないとも言えません。
また、蓄電池のメーカー保証、そして太陽光発電のメーカー保証ともに保証適用外になってしまいます。
いずれも長期間の利用が前提の製品なので、メーカー保証がなくなるのは致命的です。
トラブルや不具合の相談すら受け付けてくれなくなる可能性もあるので、対応メーカーでない太陽光発電との接続は絶対に避けましょう。
特に、設置済の太陽光発電に新たに蓄電池を導入する場合は、蓄電池の機種が絞られるため注意が必要です。太陽光発電・蓄電池の機種ごとに接続確認の取れているメーカー・機種が異なるため、事前によくチェックしておきましょう。
丸紅エネブル蓄電池では、お客様の既設太陽光発電との互換性を確認した上で、蓄電池の機種をご提案します。
蓄電池は寿命を理解して長持ちさせよう
蓄電池の寿命は、目安としてメーカー保証年数の10年〜15年が1つの区切りとなっています。
しかしながら、実際には蓄電池の寿命はサイクル回数であり、10年・15年が経過しても蓄電池はまだ使うことが可能です。
ただ、そこからどれだけ寿命を長くできるかは、蓄電池の使い方や周辺環境などによって変わります。蓄電池を普段から正しく使うという日々の積み重ねが、なによりも蓄電池を長持ちさせる秘訣です。蓄電池を最大限に活用できるよう、蓄電池の寿命の仕組みとポイントをよく理解しておきましょう。
-

お気軽にお問い合わせください。